












9月26日(日)18時より、南風原中学校35期生同期会が南風原町公民館にて行なわれました。南風原町観光協会では会場の設営から片づけまでさせていただきました。今回は立食パーティーでしたので、ビュッフェスタイルでご用意。舟盛り、にぎり、串揚げ、チャップステーキ、サラダなど、デザートにはシュークリーム、シフォンケーキと、女性にも喜んで頂けるメニューで、皆様にご満足して頂ける提供ができたと思います。これからの時期、今年を振り返り労をねぎらう「忘年会」新しい年の始まりを祝う「新年会」その他会合に南風原町観光協会のケータリングはいかがですか。お客様のご要望に合わせ、町内の飲食業者、小売店協力のもと準備致します。ご希望の方は南風原町観光協会までご用命ください。

南風原の魅力、伝統文化が放送されました。



9月8日(火)15日(火)夕方6時10分からのNHK沖縄放送局おきなわHOTeye「ぶらり見つけ旅」のコーナーで、観光案内所に置かれている南風原町旧字12か所のパンフレットをもとに、字津嘉山を歩き『弾痕の残る塀』や『与座家の高倉・ヒンプン』等を歩き、住人の方が直接案内してくれる様子や、字喜屋武では中村さん宅にて鰹、豚骨、豚ロースで出汁をとって作る、汁のない『ソーミンタシヤー』を食しました。山川の旧盆では午後8時に、お供え物の果物に乗って天へ戻ってくださいと言う意味で行われる『パイナップル転がし』を神里さん宅で行われた様子が放送されました。各字それぞれに特徴のある行事にアナウンサーの方も驚かれていました。

南風原の魅力、伝統文化が放送されました。



9月8日(火)15日(火)夕方6時10分からのNHK沖縄放送局おきなわHOTeye「ぶらり見つけ旅」のコーナーで、観光案内所に置かれている南風原町旧字12か所のパンフレットをもとに、字津嘉山を歩き『弾痕の残る塀』や『与座家の高倉・ヒンプン』等を歩き、住人の方が直接案内してくれる様子や、字喜屋武では中村さん宅にて鰹、豚骨、豚ロースで出汁をとって作る、汁のない『ソーミンタシヤー』を食しました。山川の旧盆では午後8時に、お供え物の果物に乗って天へ戻ってくださいと言う意味で行われる『パイナップル転がし』を神里さん宅で行われた様子が放送されました。各字それぞれに特徴のある行事にアナウンサーの方も驚かれていました。

9月15日(火)から南風原町役場ロビーにて、三日間開催された「南風原ふるさと名人活用促進展」は、17日、無事に閉会しました。
南風原ふるさと名人制度の周知と登録・活用促進をねらった当イベント。展示と同時に、名人達による実演が多彩な内容で繰り広げられています。
会場の都合上、準備期間が短かったのですが、作品が素晴らしい、という感想がいっぱいで、名人制度が地域活性になって素晴らしいという声もきかれました。
名人の実演の場では、多くの方が集まり、名人の技を手ほどきしていただき、たいへん喜んでいただきました。
1日目は、シーサー作り実演(仲村渠哲夫)の他、歌三線(野原廣信)、島そうり彫り(松田かなえ)、折り紙(知念洋子、喜友名愛子)、絵手紙(西原正幸)の実演がされました。





2日目も、癒書(のはら恵子)、歌三線(野原廣信)、ソープカービング(神里ヨシ子)、POP作り(辻慶子)、紙芝居読み語り(新垣正宏)と色とりどり行なわれました。




 癒書と歌三線のコラボという、とても斬新な試みで、迫力のあるシーンを見せてくれました。
癒書と歌三線のコラボという、とても斬新な試みで、迫力のあるシーンを見せてくれました。
野村流古典音楽保存会に所属する野原さんは、カンカラ三線、板張り三線、プリント布張り、愛用の蛇川張りの三線の音色弾き比べのほか、組踊りで弾かれる歌を解説付きで実演しました。
3日目のPOP作り実演では、城間町長も楽しそうにデコカッターで貼れパネを切る体験しました。初めての体験でこんなにスムーズに切れる町長はセンスがあると、名人の辻慶子さんが驚いていました。
紙芝居読み語り名人の新垣正宏さんは、新作の手作り紙芝居「飛び安里」を二日間読み語りました。その他に、「うさんしー」「本部満名」等の読み語りに、地元の方々は、うなずいたり、意見を言い合ったりと、わがシマの昔語りに喜んでいました。 最 後の実演は、仲本明光さんによる「しまくとぅば語り」で、しまくとぅばを守ることの大事さを語り、しまくとぅばによるなぞなぞ等でもりあがりました。



今回の南風原ふるさと名人活用促進展は、名人達がはりきって参加し、会場設営から会場見守り当番、実演、そして会場の片付けを積極的にやってくれました。まるで、学園祭を楽しむ若者のようなお顔をしていたのが嬉しくて、とてもほのぼのとさせてくれました。 ふるさと名人の皆様、お疲れ様でした。

9月15日(火)から南風原町役場ロビーにて、三日間開催された「南風原ふるさと名人活用促進展」は、17日、無事に閉会しました。
南風原ふるさと名人制度の周知と登録・活用促進をねらった当イベント。展示と同時に、名人達による実演が多彩な内容で繰り広げられています。
会場の都合上、準備期間が短かったのですが、作品が素晴らしい、という感想がいっぱいで、名人制度が地域活性になって素晴らしいという声もきかれました。
名人の実演の場では、多くの方が集まり、名人の技を手ほどきしていただき、たいへん喜んでいただきました。
1日目は、シーサー作り実演(仲村渠哲夫)の他、歌三線(野原廣信)、島そうり彫り(松田かなえ)、折り紙(知念洋子、喜友名愛子)、絵手紙(西原正幸)の実演がされました。





2日目も、癒書(のはら恵子)、歌三線(野原廣信)、ソープカービング(神里ヨシ子)、POP作り(辻慶子)、紙芝居読み語り(新垣正宏)と色とりどり行なわれました。




 癒書と歌三線のコラボという、とても斬新な試みで、迫力のあるシーンを見せてくれました。
癒書と歌三線のコラボという、とても斬新な試みで、迫力のあるシーンを見せてくれました。
野村流古典音楽保存会に所属する野原さんは、カンカラ三線、板張り三線、プリント布張り、愛用の蛇川張りの三線の音色弾き比べのほか、組踊りで弾かれる歌を解説付きで実演しました。
3日目のPOP作り実演では、城間町長も楽しそうにデコカッターで貼れパネを切る体験しました。初めての体験でこんなにスムーズに切れる町長はセンスがあると、名人の辻慶子さんが驚いていました。
紙芝居読み語り名人の新垣正宏さんは、新作の手作り紙芝居「飛び安里」を二日間読み語りました。その他に、「うさんしー」「本部満名」等の読み語りに、地元の方々は、うなずいたり、意見を言い合ったりと、わがシマの昔語りに喜んでいました。 最 後の実演は、仲本明光さんによる「しまくとぅば語り」で、しまくとぅばを守ることの大事さを語り、しまくとぅばによるなぞなぞ等でもりあがりました。



今回の南風原ふるさと名人活用促進展は、名人達がはりきって参加し、会場設営から会場見守り当番、実演、そして会場の片付けを積極的にやってくれました。まるで、学園祭を楽しむ若者のようなお顔をしていたのが嬉しくて、とてもほのぼのとさせてくれました。 ふるさと名人の皆様、お疲れ様でした。

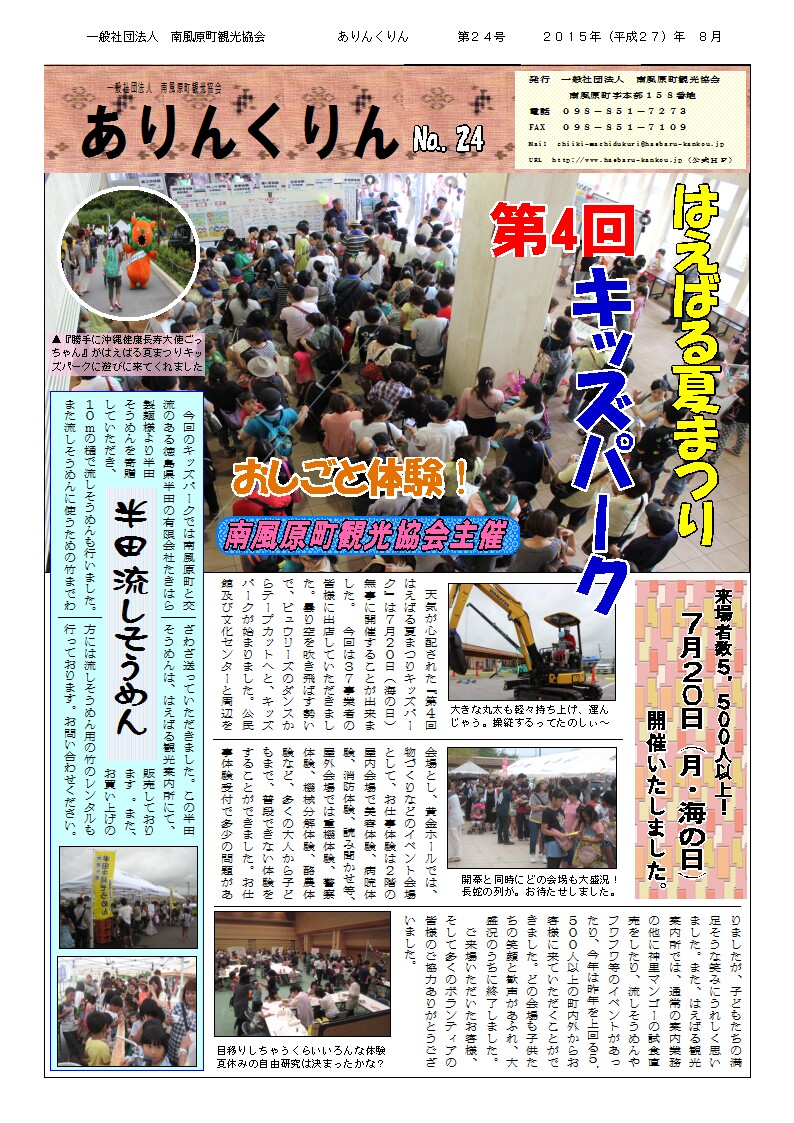

6月26日(金)
平成27年度町老連新旧役員歓送迎会がちむぐくる館にて行なわれ、こちらのケータリングを
観光協会で行わせていただきました。



お料理は町内の飲食業者の会員の皆さんが、お客様にあわせ工夫をこらし作ってくれています。
お客様はお酒も進み、カラオケで盛り上がり楽しんでいただけた様子。
職員の 「おもてなしの心」にも、ますますの磨きがかかりました。



今後、ケータリング希望がございましたら、どうぞお気軽に南風原町観光協会までご連絡ください<(`^´)>

現在はえばる観光協会では、かすりの道ツアーを行っていますが、さらなるコースの増進の為、
ガイドさんの研修会を行いました。
6月27日(土)(晴天)
7名のガイドさんと、5名の観光協会職員。そして、今回ガイドさんの為の講師 金城清さん
(南風原町産業振興課)を先頭に津嘉山を歩きました。
東ぬんどぅるちからスタート、津嘉山の小学校、幼稚園、公民館、大綱曳きの綱作りのお話や、
弾痕の壁、飛び安里の借家跡、南風窯では素敵な庭でゆったり休憩をしながら、ガイドの勉強をしました。
皆さん真剣な表情で、時に笑いながら無事に研修会が終了。
来月には、あらためて集まりコース作りをしてゆきます。
どんなコースになるのか、どうぞ皆様ご期待ください。





