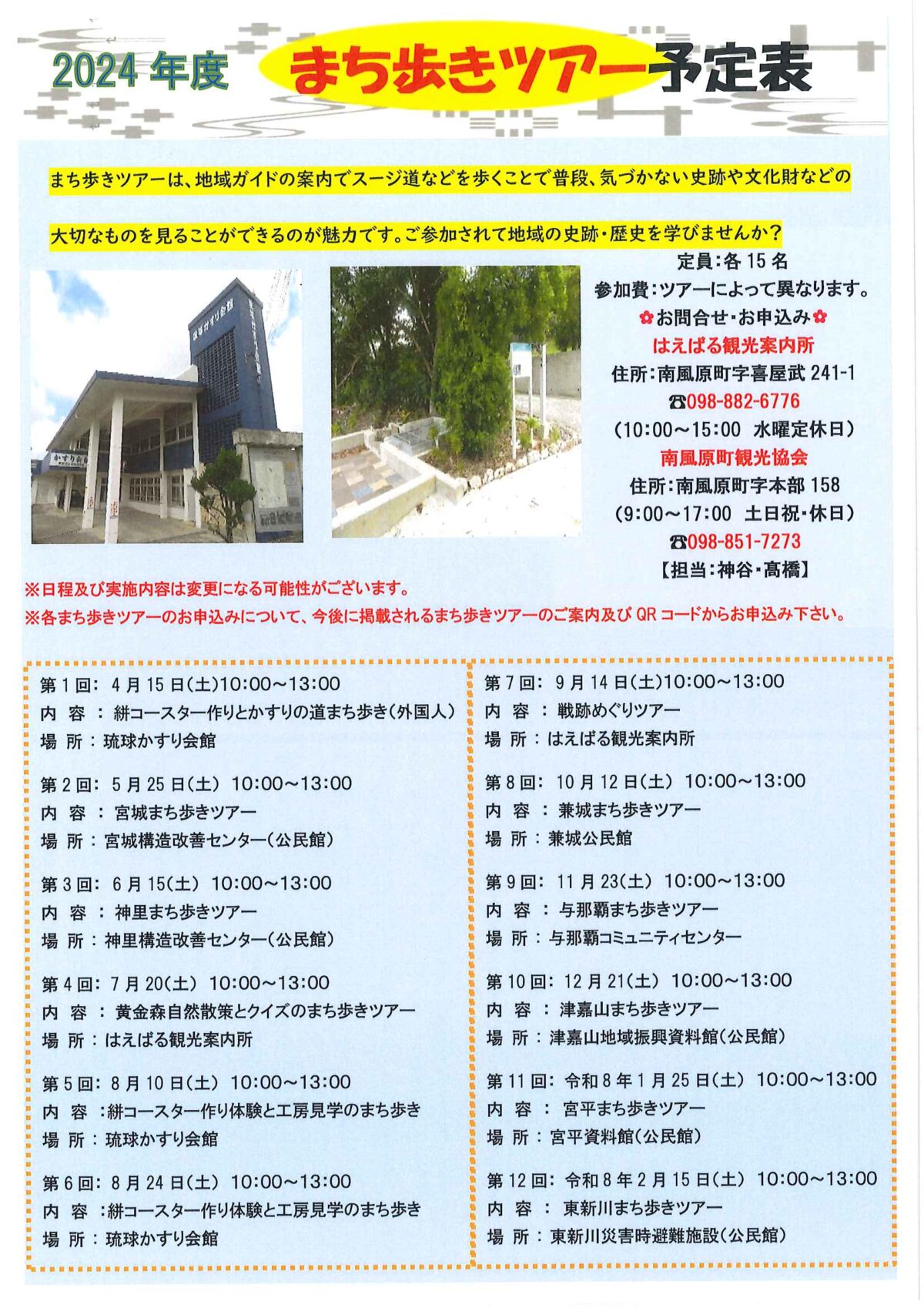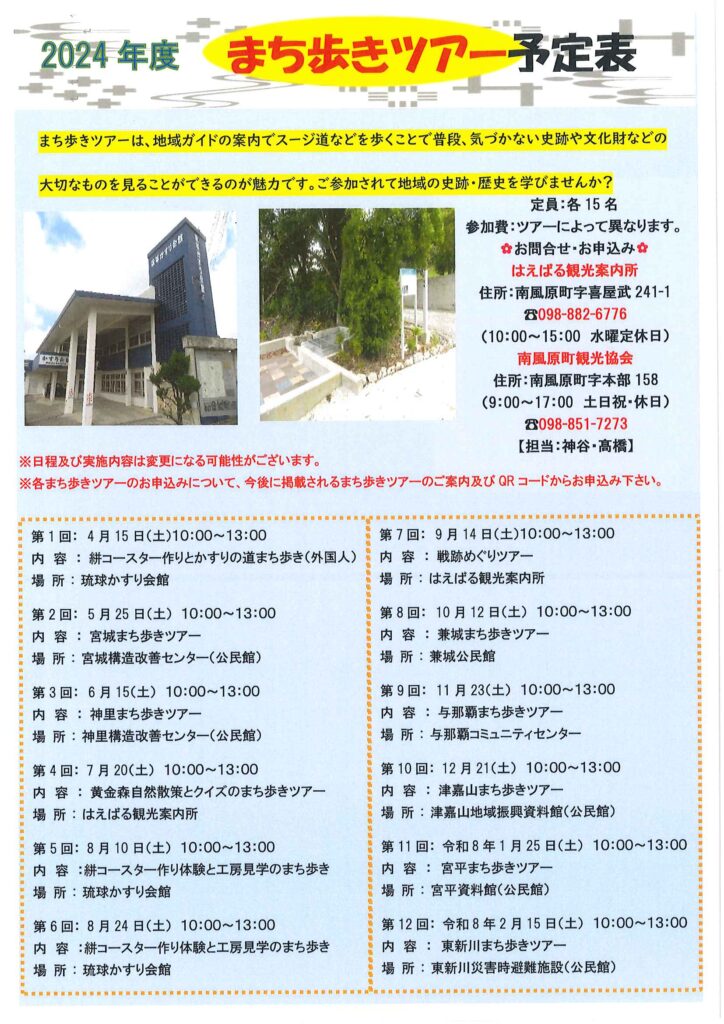第2回ガイド研修が7月13日、南風原文化センターで開催され12人が参加しました。この日は字与那覇地域ガイドの新垣敏氏が「与那覇の歴史と伝説」をテーマに講師を務めました。まず、与那覇地区が戦後劇的に変化したことについて語り、かつては与那原の浜の波音が聞こえるほど静かだったエピソードを紹介しました。
また、地元に語り継がれる浦島伝説の主人公、ウサンシー(穏作根子)の屋敷跡といわれる「御殿小」や、ウサンシーが眠ると伝わる「ウサン嶽」などについて写真をまじえながら説明しました。県外の浦島伝説とも比較しながら、与那覇と同じく海のない地域でも浦島伝説が残ることに触れました。このほか、トーマの御嶽、ノロ殿内、与那覇グスクなどの聖地・遺跡や、綱引きといった伝統行事についても詳しく解説しました。

この日の参加者に対してアンケートを実施したところ、11人から次のような回答を得ました。
- 本日の講座はいかがでしたか?
- よく理解できた(8人) ②まあまあ理解できた(2人) ③あまり理解できなかった(1人)
・与那覇グスク北方の石畳の説明(存在理由)
・馬場跡の場所
・基礎的な知識(沖縄に関すること、南風原のこと、地域のこと)がまったく足りないことが分かりました。
- 今回の講座の内容は、実際のガイドに活用できそうですか?
- 大いに活用できる(8人) ②活用できる(3人) ③あまり活用できない(0人) ④活用できない(0人)
・場所の案内だけでなく、歴史的な人物や森、川(海)、過去と現在とのかかわりの中で、今も御嶽が残っていることを知ったから
・写真もたくさんあったし、前回聞けなかった部分が聞けた
・著名な箇所や人物の様子など参考にできた
・与那覇の地理的側面、考古学的な遺跡、遺物などの事例を詳しく説明されたので、大変興味深く聞くことができました。講師の方の深い知識とユーモアをまじえた話が大変参考になりました
・ウサンシー伝説について理解が深まった
・歴史的背景がよくわかる
・学びたい気持ちが高まったから
- その他、ご意見、ご感想、質問などがあればご記入ください
・アーカイブ的に過去と現在および、他の地域との比較をしながらの説明は、イメージに残りやすく、与那覇地区の浦島伝説は記憶に残った。ありがとうございました。
・約1時間半、実際に歩いて見て回った感じがした。実際に歩かなくても、現地に行った感じがした。
・講師のプロフィールも紹介してほしい。
・神谷さんの説明がとても分かりやすくて、ありがたいです。ありがとうございました。
・基本的な概説書や参考文献などがあれば教えてください。 第2回ガイド研修が7月13日、南風原文化センターで開催され12人が参加しました。この日は字与那覇地域ガイドの新垣敏氏が「与那覇の歴史と伝説」をテーマに講師を務めました。まず、与那覇地区が戦後劇的に変化したことについて語り、かつては与那原の浜の波音が聞こえるほど静かだったエピソードを紹介しました。
また、地元に語り継がれる浦島伝説の主人公、ウサンシー(穏作根子)の屋敷跡といわれる「御殿小」や、ウサンシーが眠ると伝わる「ウサン嶽」などについて写真をまじえながら説明しました。県外の浦島伝説とも比較しながら、与那覇と同じく海のない地域でも浦島伝説が残ることに触れました。このほか、トーマの御嶽、ノロ殿内、与那覇グスクなどの聖地・遺跡や、綱引きといった伝統行事についても詳しく解説しました。
この日の参加者に対してアンケートを実施したところ、11人から次のような回答を得ました。
- 本日の講座はいかがでしたか?
- よく理解できた(8人) ②まあまあ理解できた(2人) ③あまり理解できなかった(1人)
・与那覇グスク北方の石畳の説明(存在理由)
・馬場跡の場所
・基礎的な知識(沖縄に関すること、南風原のこと、地域のこと)がまったく足りないことが分かりました。
- 今回の講座の内容は、実際のガイドに活用できそうですか?
- 大いに活用できる(8人) ②活用できる(3人) ③あまり活用できない(0人) ④活用できない(0人)
・場所の案内だけでなく、歴史的な人物や森、川(海)、過去と現在とのかかわりの中で、今も御嶽が残っていることを知ったから
・写真もたくさんあったし、前回聞けなかった部分が聞けた
・著名な箇所や人物の様子など参考にできた
・与那覇の地理的側面、考古学的な遺跡、遺物などの事例を詳しく説明されたので、大変興味深く聞くことができました。講師の方の深い知識とユーモアをまじえた話が大変参考になりました
・ウサンシー伝説について理解が深まった
・歴史的背景がよくわかる
・学びたい気持ちが高まったから
- その他、ご意見、ご感想、質問などがあればご記入ください
・アーカイブ的に過去と現在および、他の地域との比較をしながらの説明は、イメージに残りやすく、与那覇地区の浦島伝説は記憶に残った。ありがとうございました。
・約1時間半、実際に歩いて見て回った感じがした。実際に歩かなくても、現地に行った感じがした。
・講師のプロフィールも紹介してほしい。
・神谷さんの説明がとても分かりやすくて、ありがたいです。ありがとうございました。
・基本的な概説書や参考文献などがあれば教えてください。




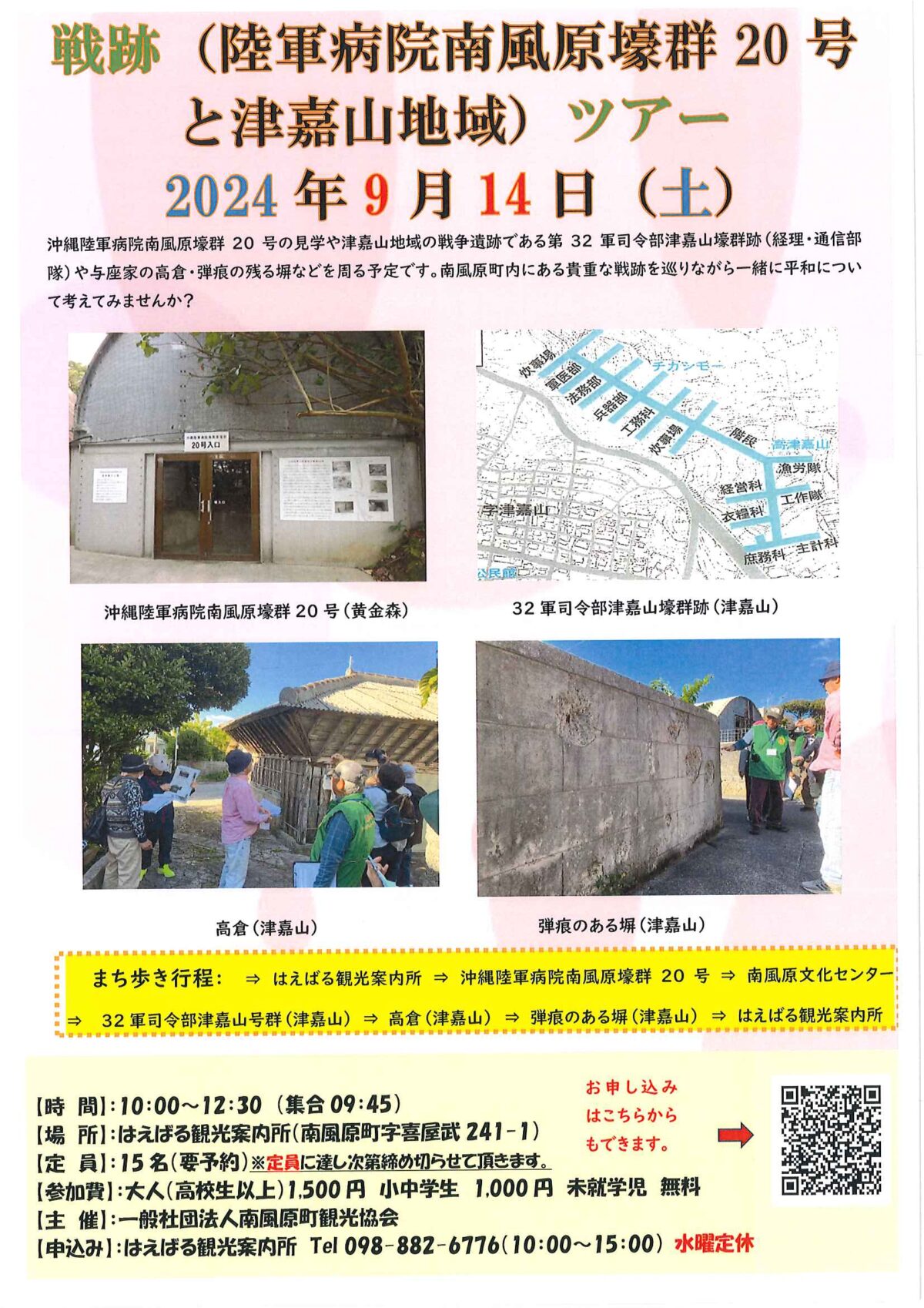
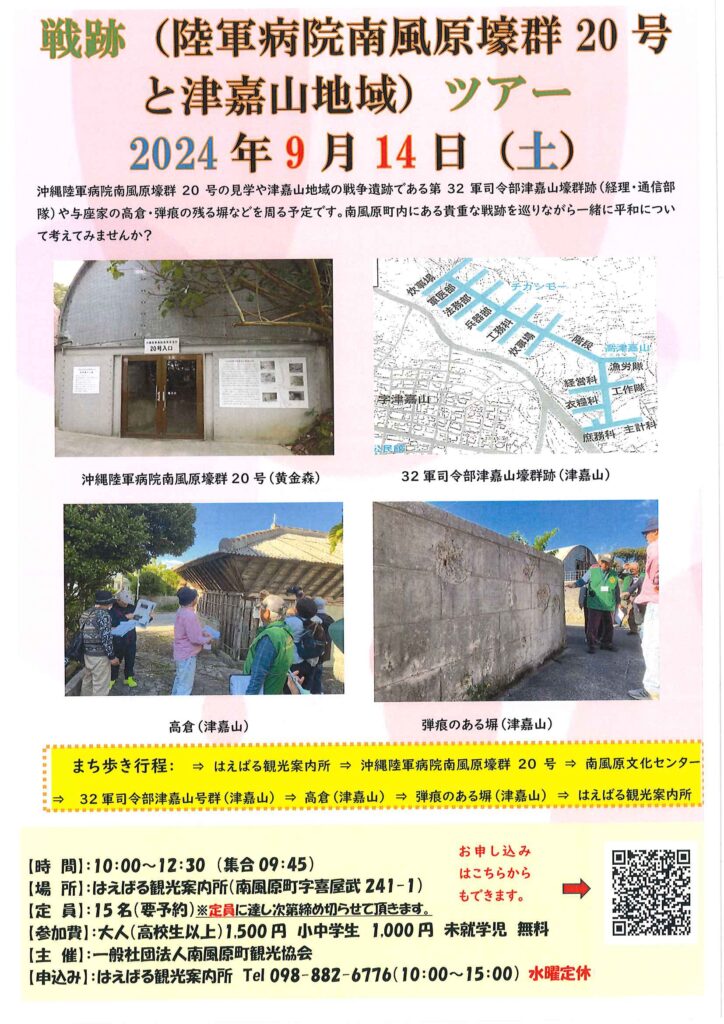
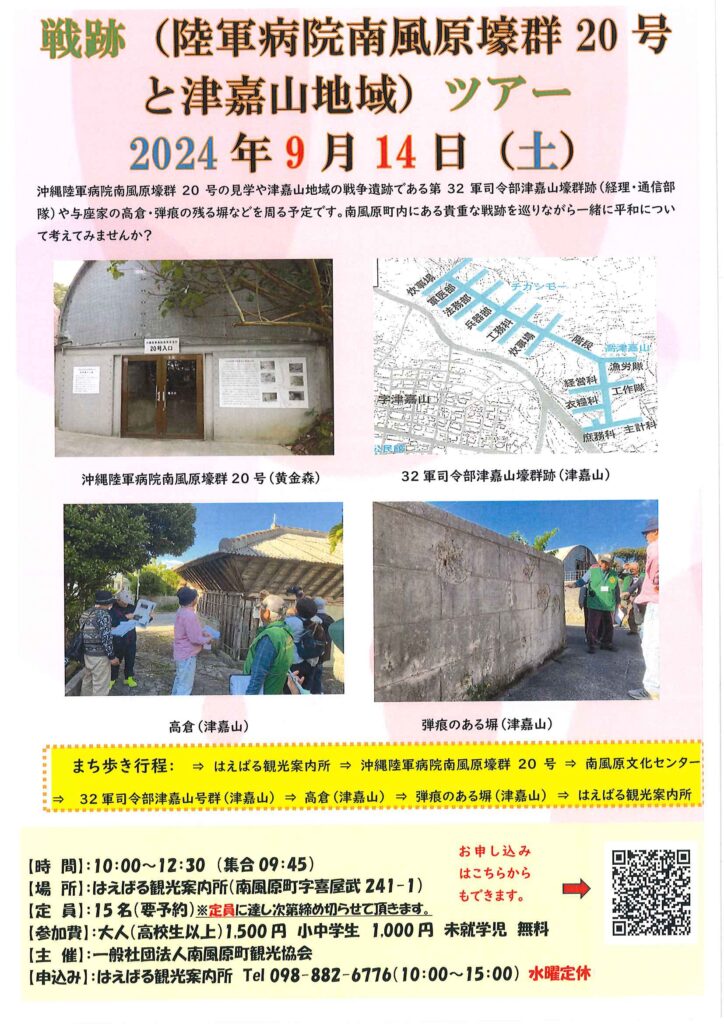



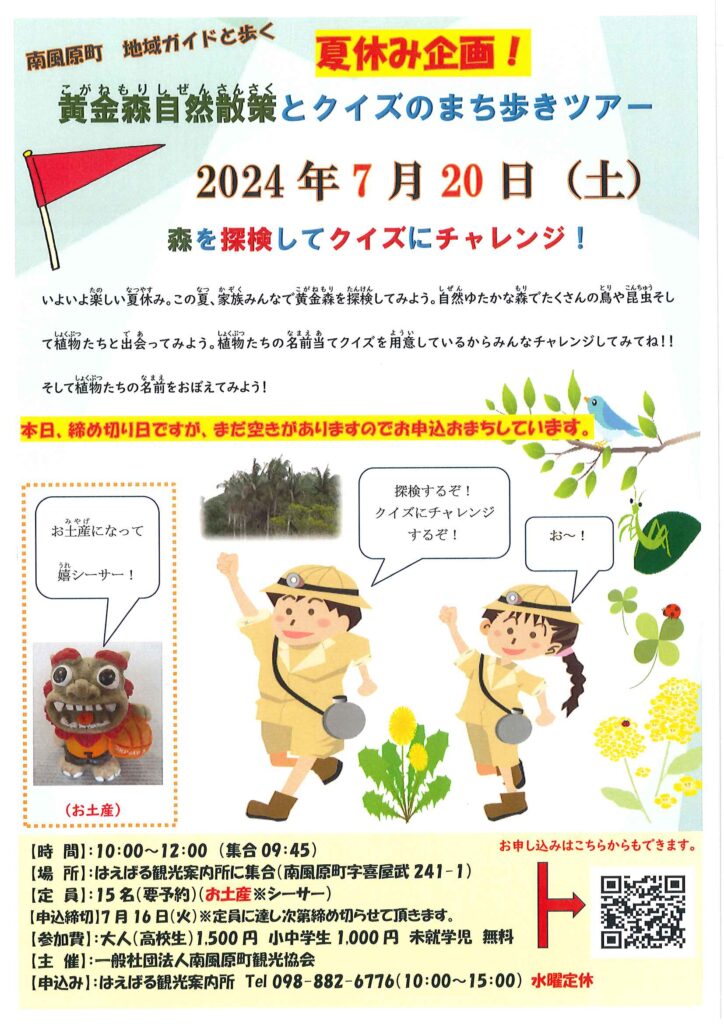
-1200x1698.jpg)
-1-724x1024.jpg)
-2-724x1024.jpg)
-1200x1698.jpg)
-1-724x1024.jpg)